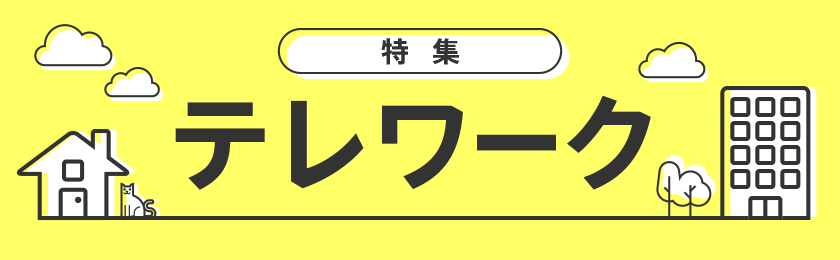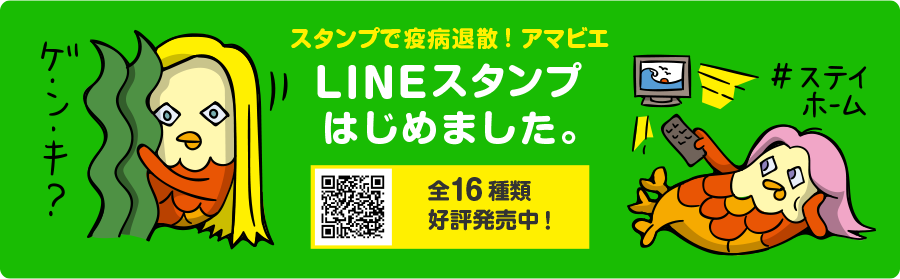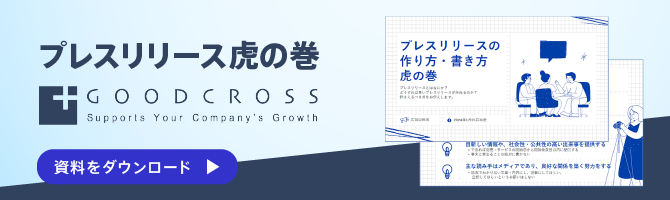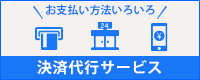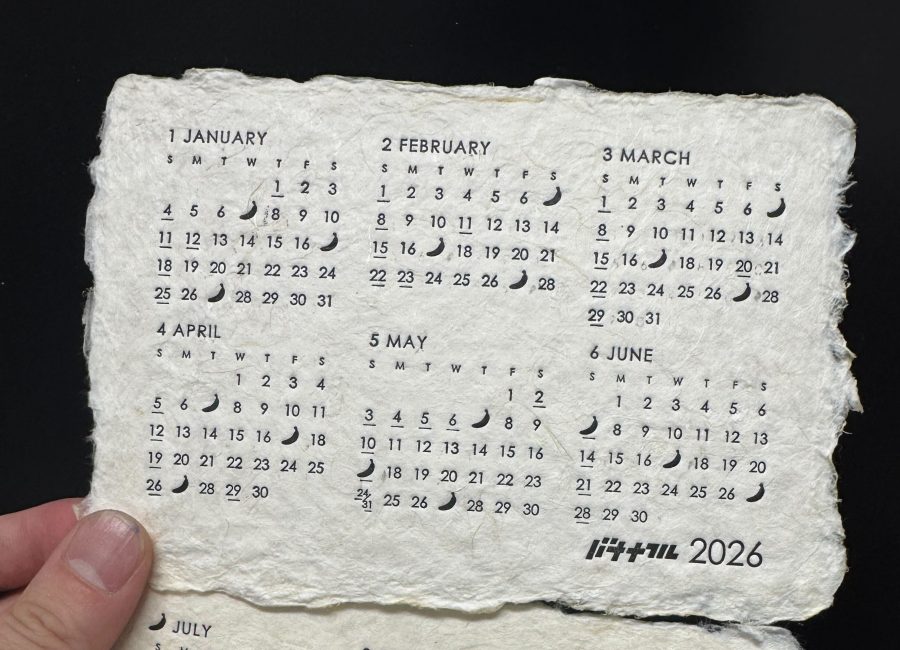

最近、全国各地で雷の多い日が続いています。
夕立とともに空に走る稲光、その轟音に驚かされることもしばしば。
しかし、昔から日本では「雷が多い年は豊作になる」と言い伝えられてきました。
この言い伝えには、単なる迷信ではない自然との関係性が潜んでいます。
そして、雷を意味する「稲妻(いなずま)」という言葉にも、私たちの暮らしに深く根付いた稲作文化とのつながりが込められているのです。
雷と稲作の不思議な関係
雷が多いと稲がよく育つ——そう信じられていた理由のひとつに、雷の際に発生する「窒素」が関係しています。
雷によって大気中の窒素が地上に降り注ぎ、それが土壌に栄養を与えることで、稲の生育に好影響をもたらすと考えられていたのです。
もちろん、これは近年になって科学的にも一部裏付けられていますが、昔の人々はそうした現象を「神の恵み」として直感的に捉え、雷を吉兆と見なしてきました。
「稲妻」とは、まさに稲の成長を支える存在
さて、「稲妻」は、なぜ「稲の妻」と書くのでしょうか?
これにはいくつかの説がありますが、ひとつの有力な説は、雷(稲妻)を「稲の実りを助ける存在」すなわち「稲の伴侶」として表現したというものです。妻とは単なる配偶者ではなく、「支え合うもの」「大切な相手」という意味合いも含まれていたのでしょう。
また、古語では「妻(つま)」が「端(はし)」や「先(さき)」を意味することもあり、「稲の先端に光が走る」という意味から、「稲妻」という表現が生まれたとも言われています。
自然とともに生きた言葉
私たちの言葉には、自然と密接に結びついた表現が数多く残されています。「稲妻」もその一つ。
雷が鳴り響く空を見上げながら、そこに豊作の兆しを見出してきた先人たちの知恵と感性が、この一語に宿っているのです。
おまけ
当社はbeecallというコールセンター・カスタマーサポートも運用しており、24時間365日対応しています。
言葉を扱う者として正しい言葉の使い方を意識し、日々受電を行っているので、ご興味のある方はぜひ、beecallのサイトもご覧ください。