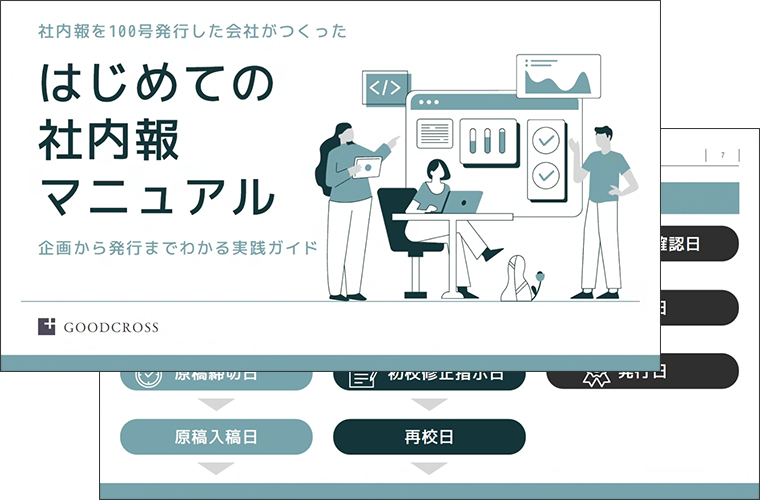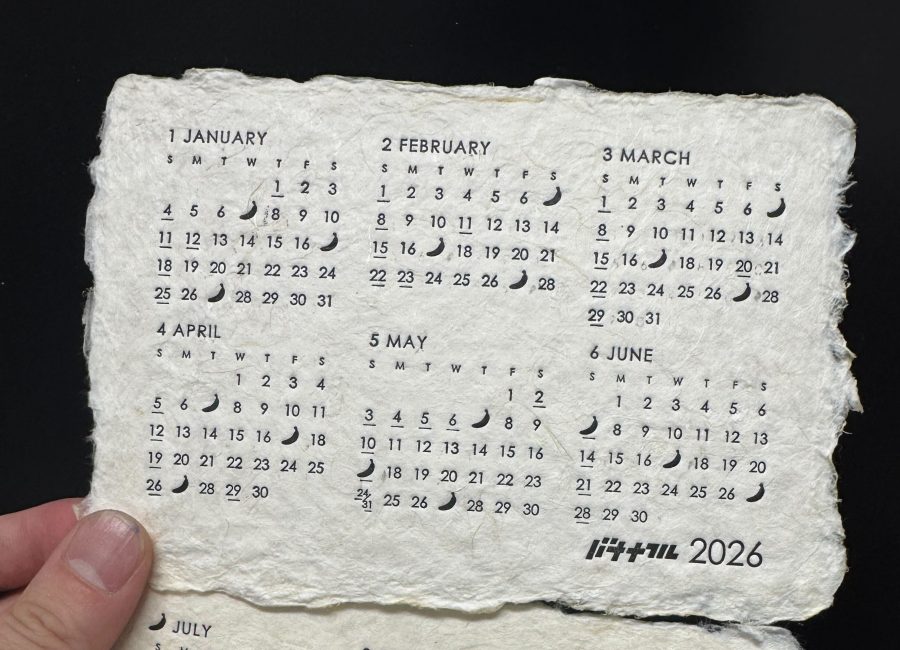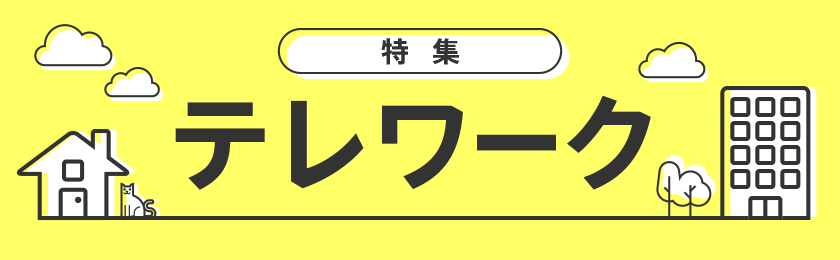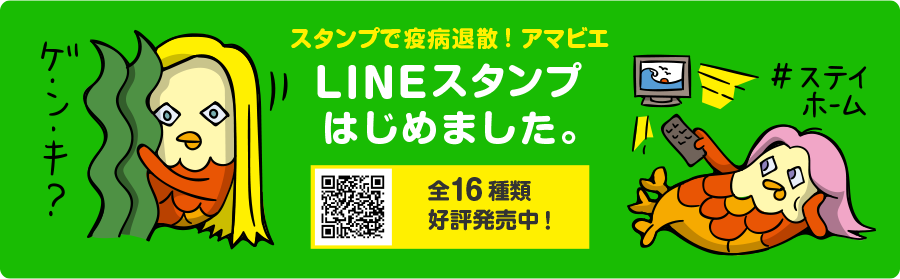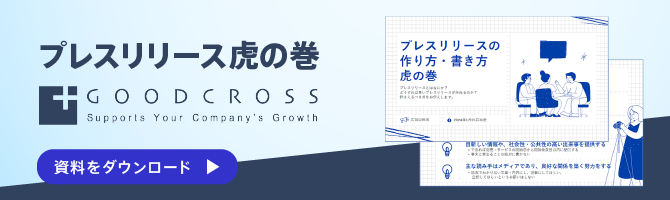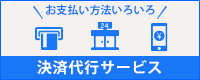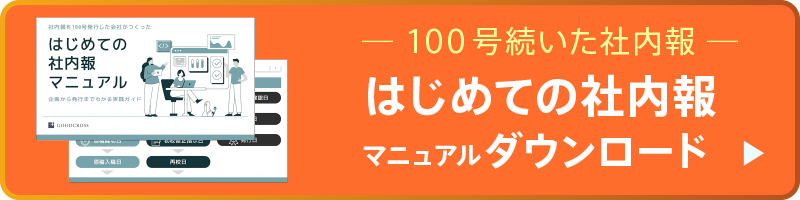まだまだ夏真っ盛り。
暑い日が続きますが8月7日に立秋を迎え、暦の上では秋となりました。
今回ご紹介するのは8月の和名である「葉月」の語源についてです。
なぜ8月は「葉月」と呼ばれるようになったのでしょうか?
「葉月」の語源とは
「葉月」の由来については、いくつかの説があります。
代表的なものを見ていきましょう。
葉落ち月(はおちづき)
旧暦の8月は現在の9月上旬から10月上旬にあたります。
この時期は、木の紅葉が進み、葉が落ち始める季節。
葉が落ちるから葉落ち月。
秋の始まりを感じさせる美しい由来ですね。
穂張り月(ほはりづき)
稲穂が実り、穂先がその重みで垂れ下がっていく様子を「稲の穂が張る」と言います。
これにちなんで「穂張月」が「葉月」の語源とする説もあります。
稲作は古くから日本人の暮らしと深く結びついています。
水無月や文月のように、「葉月」もお米に由来した説があるのです。
初来月(はつきづき)
渡り鳥の雁が日本に渡ってくる時期であることから、雁が初めてくる月ということで「初来月」が語源だとする説もあります。
雁は秋の季語としても知られており、この説もまた、葉月が秋の始まりを感じさせる月であることを物語っています。
いかがでしたか?
「葉月」という美しい響きの背後には、日本人の自然への感受性や、四季の移ろいを大切にする文化が息づいています。
次回は9月の和名「長月(ながつき)」の由来についてご紹介します。どうぞお楽しみに!
おまけ
当社はbeecallというコールセンター・カスタマーサポートも運用しており、24時間365日対応しています。
言葉を扱う者として正しい言葉の使い方を意識し、日々受電を行っているので、ご興味のある方はぜひ、beecallのサイトもご覧ください。
参考:ウェザーニュース(8月の異名「葉月」語源からは早くも秋の気配) / 歴史民俗資料館(葉月|歴民コラム 三春歳時記5|三春町歴史民俗資料館))